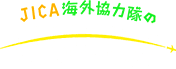2026/02/03 Tue
生活 観光
任国外旅行を終えて
私がドミニカ共和国にきて一年と六か月がたった。この国の人々、風土、食べ物、文化がやっと身体になじみ、自分の中にある凝り固まった何かと、化学反応を起こす、くすぶりを感じている。
さて今回のテーマである任国外旅行の話をする前に、私がドミニカ共和国で何をしているかについて簡単に説明する。職種は食用作物・稲作栽培。具体的な活動としては、San Juan de la Maguana県において、コメの収量向上および環境保全型農業の推進を目標に、農務省と連携しながらその達成に向けた取り組みを行っている。最新技術の提供というよりも、地域の土地条件や気候特性、農家の実情を踏まえ、実地的な栽培管理方法を模索していくことに重きを置いている。
では今回私が任国外旅行に行くことを決めた経緯から話していく。当時はあまり任国以外の国に行くことに興味がわかなかった。行って何をするのか、たくさんお金がかかるだろうな、危ないかもしれないと、思い出せば、行かない理由ばかりを考えていた。そんなとき同じドミニカ共和国に派遣されている先輩から、任国外旅行の話を聞いた。「任国外旅行は自分のいる国のことを知るために行くんだ。」先輩のこの言葉に妙に納得してしまった私は任国外旅行に行くことに決めた。
ブラジルとエクアドルに行った。中米の国にも行きたかったが、また別の機会に。
この二つの国を訪れてまず感じたのは、ドミニカ共和国とは異なる空気感であった。
ドミニカ共和国では地域にもよるが、全体的に私に対する態度は、異国人という認識が私を見るときのフィルターとして存在しているように感じる。ここに私がこの国で感じる窮屈さがある。このフィルターによって、私は自分の立場を改めて認識させられる。言い換えれば、「お前はマイノリティである」ということを否応なく突き付けられるということだ。
対してブラジルやエクアドルでは、そこにただいる一人の人として、私が客という立場なら、ほかの客と変わりない客として認識されている感覚があり、そのフィルターをもとから持っていないように感じられた。そこには寛容さではなく、ごく自然な営みの範疇に、私がいるような感覚だった。
この違いを作りだしている要素とは何か。歴史的背景、社会構造、人々の価値観。簡単に思いつくものを並べると、このようになるだろう。ここから述べる内容はあくまでも私の主観に基づくものであり、どの要素においても専門的な知見を有しているわけではないので、私が知っている範囲で整理していく。
私の任国であるドミニカ共和国もブラジルもエクアドルも、いずれもかつては他国の植民地であった。しかし、そこから国家として認められるまでのストーリーに、ドミニカ共和国とブラジル、エクアドルには大きな違いがある。国家が自らをどう語ってきたか、つまり「我々とは何者か」をどう定義してきたかの違いがある。
ドミニカ共和国の歴史は、コロンブスの来航に端を発し、もともとこの地に居住していたTaíno(タイノ族)は早い段階で人口的に消滅した。その結果、植民地期以降の社会は、主としてスペイン系とアフリカ系という二つの系譜を軸として形成されてきた。
スペインからの分離を達成した直後、隣国ハイチによる統治を受けた。その後、1844年に独立国家として成立したものの、国は依然として不安定であり、1861年には自らスペインへの再併合を要請するに至っている。
この歴史的経緯は、ドミニカ共和国における国民意識の形成に大きな影響を及ぼしている。注目したい点として、同国の独立記念日および現在の国名の制定を祝う国家的記念日は、三世紀以上に及ぶスペイン植民地支配からの分離(1821年)を記念するものではない。1822年から1844年までの約20年間、現在のドミニカ共和国とハイチが共有するイスパニョーラ島全域を統治していた、かつて奴隷であった人々によって建国された黒人国家ハイチからの分離を記念するものである(DW, 2024)。
この事実は、ドミニカ共和国におけるナショナル・アイデンティティが、「植民地支配からの解放」という一般的な独立の物語ではなく、「ハイチからの分離」という対抗的・排除的な歴史経験を軸として構築されてきたことを示している。こうした歴史的記憶は、今日に至るまで反ハイチ感情や人種による境界意識の形成に深く関与しており、「No somos racistas, no queremos haitianos y punto (我々は人種差別主義者ではない。しかしハイチ人は望まない)」という言説が社会的に反復される背景の一端を成している。
一方で、ブラジルやエクアドルは国家として成立する以前から、すでに多様な人々が同じ社会空間の中に存在していた。ブラジルには、ポルトガル系植民者、アフリカから連行された多数の被奴隷民、さらには多様な先住民社会が存在していた。エクアドルにおいても、スペイン系、メスティーソ、アフリカ系、多数の先住民族が暮らしており、いずれの国においても、植民地期を通じて形成された人口構成は、単一的なものではなかった。特にブラジルでは、国家形成後も移民政策を通じて多様な人々を受け入れてきた歴史がある。
私がサンパウロ移民博物館で目にしたのは、移民が例外的な存在ではなく、国家の形成過程そのものに組み込まれてきたという事実であった。
このように、ブラジル、エクアドルでは、「多様性そのものが国家である」、「混血こそが国民性」というストーリーが共有されてきた。
対照的に、ドミニカ共和国は長らく、「ハイチとは違う」、「黒人ではない」、「スペイン系である」という否定によって自己を定義してきた国家観を有してきた。すなわち、我々は「誰ではないのか」という、ハイチ人との否定を通じた自己定義の構造が、現在に至るまで社会の深層に横たわっている。
これこそが、私がドミニカ共和国とブラジル、エクアドルの間で感じてきた違いの正体であった。
「否定により自己を定義する国家観」という言葉には、どこか身に覚えのある感覚がある。特に明治以降の近代国家形成時には、日本人が「アジア人として一括りにされたくない」「文化も価値観も異なる」という主張が強くあった。現在においても、その形は変化しているものの、同じような感覚は完全には消えていないように思われる。
この主張は一部において事実として正しい。しかし、ここで重要なのはなぜこの主張が感情的な強さを帯びているのかということだ。その背景には、単なる文化的差異ではなく、「同一視されること」そのものに対する強い抵抗感がある。
ここで少し日本史を振り返ってみたい。日本の近代国家形成期を簡潔に言えば、それは、西洋に追いつくために、アジアの中の後進国であるという自己像を否定し続けた時代であった。代表的な思想として挙げられる「脱亜入欧」は、単なる外交路線ではなく、「我々はアジアとは違う存在である」という自己定義の宣言であった。
つまり日本もまた、何者であるかというよりも、何者ではないかによって、近代化の時代において、自国を位置づけてきた国家であったと言える。
ではなぜアジアと一括りにされることに対して、強い抵抗感があるのか。
それは近代化以前の自己へと引き戻されることへの、無意識の恐怖に由来するのではないだろうか。そこにあるのは差別感情というよりも、むしろ歴史的経験に刻み込まれたトラウマに近いものだと、私は感じている。
その結果として、違いを過度に強調することや、距離を取ろうとする反射的な防衛反応が生まれやすくなる。外から見ればそれは優越的な態度のようにも映るが、むしろ構造的には逆であり、自己定義が不安定だからこその反応ともいえる。
「我々は何者なのか」、「どこに属するのか」という問いに未だ答えは出ていない。
まさに宙づりの状態で揺れているのだ。
もう一度話をもとに戻す。私がブラジル、エクアドルで感じた、フィルターを介さない、彼らのごく自然な営みの範疇に自分がいたという感覚と、ドミニカ共和国で感じる窮屈さ――否応なくフィルターを下ろされているという感覚――は、フィルターをもともと持っている者にしかわからない感覚だった。つまり、私こそがフィルターの持ち主であったのだ。ドミニカ共和国で感じる窮屈さの正体は、まさに自分自身がたどっている歴史の重なりを、他者の姿を通して見せつけられているという、身に覚えのある感覚――自己嫌悪とも、自己投影とも言えるものだった。
だが、いつまでもそういった悩みに囚われていてはいけない。自転するだけでは、時間は進んでも、身体はそこから動いていない。部屋に閉じこもっているだけでは、世界は動かない。ザラつく現実に触れ、足を、手を、頭を動かし、今ここで何をするか。
無限の反省ではなく、事物それ自体へ。
ここを新たな出発点とし、改めて、「国際協力とはなにか」という問いについて考えていきたい。
最後に、今回旅に同行してくれた同期隊員には感謝をしている。
2024年度1次隊 佐々木 快
・参考文献
- Deutsche Welle. (2024).“No somos racistas, no queremos haitianos y punto”: la historia que calienta la frontera entre República Dominicana y Haití.
https://www.dw.com/es/no-somos-racistas-no-queremos-haitianos-y-punto-la-historia-que-calienta-la-frontera-entre-rep%C3%BAblica-dominicana-y-hait%C3%AD/a-71222694


SHARE