2025/06/03 Tue
活動
環境教育/コロンビア日記2(1年目の活動紹介)


こんにちは。
コロンビア共和国に環境教育の隊員として派遣中の、三井貴博です。
今回は、1年目の活動内容についてご紹介します。
1. 活動の大まかな流れ(1年目)
(1) 2024年2月
コロンビアの首都に到着、各種説明、語学研修、安全対策研修、着任式 等
(2) 3月~4月
配属先であるヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・プレセンタシオン学校(以下、「配属先」と示します)に移動し、課題の把握や活動計画の作成
(3) 5月~7月
配属先の各学級で1巡目の授業と実習
(4) 8月~10月
配属先の各学級で2巡目の授業と実習
(5) 11月~2025年1月
1年目の振り返りと2年目の準備
2. 配属先について
(1) 概要
公立の初等・中等教育一貫校です(写真1、2)。
午前、午後、夜の3部制になっており、それぞれで異なる児童・生徒が学校に来ます。
3歳から18歳の児童・生徒が約2600人(全75学級)、教職員は約100人います。
校舎は2つあり、敷地面積は計20,000 m^2ほどあります。
キリスト教に基づく学校行事が、頻繁に行われています。
各種大会(サッカーやカラオケ 等)も、たまに、突然行われます。

(2) JICA海外協力隊への要請内容
配属先の学校長から、以下の要請がありました。
ア 児童・生徒による、校内のごみのポイ捨てを無くしたい。(要請書にも記載あり)
イ 緑化を推進して、校内をより美しくしたい。(要請書に記載はなく新たに追加)
活動期間は2年あるので、1年目は「ア」に、2年目は「イ」に取り組むことになりました。
3. 活動の細かな内容
(1) 活動計画の作成
着任後、約2か月かけて配属先を隅々まで観察し、児童・生徒や教職員に聞き取り作業を行いました。
それを基に配属先の内部環境と外部環境それぞれの、プラス要因とマイナス要因を明確にし、クロスSWOT分析を行いました。
教職員や中等教育課程の生徒から意見をいただきながら内容を検討しました。
その結果、授業や実習の内容、それを行うのに適した時期、留意点 等が明確になりました。
活動計画も完成したので、全教職員が集まった会議の場で、その内容を説明しました(写真3、4)。
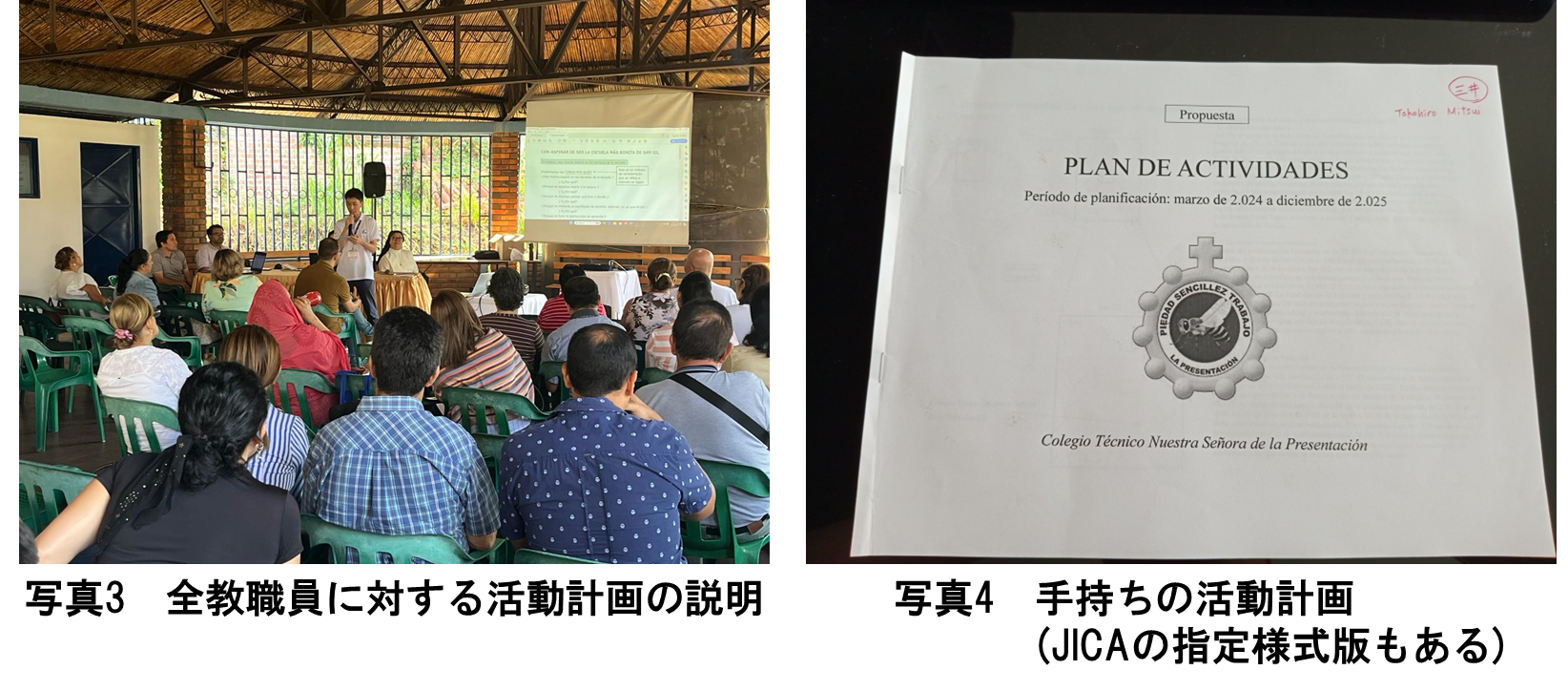
(2) 授業の実施
本ページの冒頭の写真にあるように、配属先では校内に様々なごみがポイ捨てされています。
ポイ捨てを無くすために、各学級で授業を2回、計6か月かけて行いました(写真5、6)。
実際に校内でポイ捨てされている8種類のごみ(ペットボトル、缶、ガラス、ビニール袋、食べかけのりんご 等)の写真を見せて、それらが自然に分解される時間はどれくらいかかるのかを教えました。
また、ごみを分別して捨てる理由や、そもそも環境とは何なのか、なぜ環境を守る必要があるのかということを授業の中で扱ってきました。
児童・生徒の理解が深まるよう、身近な物を例に出して説明することを意識しました。

(3) 実習の実施
「3の (2)」に併せて、各学級で2回の実習を行いました(写真7、8)。
実習内容は校内のごみ拾いで、拾ったごみを正しく分別して捨てる練習も行いました。
どの学級も、意欲的にごみ拾いに取り組む姿勢が見られました。
また、リサイクルを推進する上で、ごみの分別が重要であることを改めて学習しました。

(4) 教職員への技術移転
環境教育で扱う内容は、教科を横断した指導をしやすいものが多くあります。
例えば私の場合は理科、技術、農業の教員免許を持っており、理科では物化生地いずれの分野も、技術ではエネルギー変換や生物育成の分野 等、指導内容に環境教育を関連付けさせることができます。
そのため配属先でも、各教職員の担当教科に関係なく、環境教育の指導手法を理解していただきたいということを伝え続けてきました。
2年の間で、私が行う授業や実習を見て、指導手法を理解することを推奨してきました。
また、授業ごとに学習指導案を作成して全教職員に配布し、模擬授業も行いました(写真9、10)。

(5) 外部のコンペティションへの参加
各学級で2回の授業が終わって落ち着いた頃に、隣県の大学で「環境問題」に関するコンペティションがありました。
配属先の課題に対する分析内容や、授業と実習の両面から課題解決に取り組んできていることが高く評価され、賞金(約133,000円)をいただきました。
この賞金は、2年目の活動で必要になる機械や道具の購入に充てることにしました。
4. 配属先の人々の行動変容
(1) ごみ拾いの習慣化
配属先では午前と午後にそれぞれ長めの休み時間があります。
その時間に、児童・生徒はお菓子を食べたり、ジュースを飲んだりすることが自由にできます。
しかし休み時間が終わると、校内の床には様々なごみが落ちています。
私がごみ問題に関する授業をした後から、初等教育課程のそれぞれの担任が、積極的に児童へごみ拾いを指導するようになりました。
そして長い休み時間の終わり際に、約20学級の児童によるごみ拾いを行うことが、毎日の習慣となりました。
(2) 教職員の意識改善
ポイ捨てをしないよう児童・生徒に指導することは、これまで配属先で行われていませんでした。
しかし最近は教職員も児童・生徒に指導する機会が、以前よりは増えました。
私がポイ捨てに関する授業をしたことで、教職員が同様の指導をしやすい雰囲気ができてきているのかもしれません。
(3) 一部の教職員が環境教育を実施
初等教育課程にある2つの学級では、私が授業をしてしばらく経った頃(児童が学習内容を忘れているであろう頃)に、それぞれの担任が児童にもう一度指導していることもありました。
併せてごみ拾いを行う様子も見られました(写真11)。
このような形で、環境教育が継続的に行われて良かったです。

(4) 休み時間にごみ箱を持ち運ぶ
「4の (1)」に記載したとおり、配属先では休み時間におやつを食べます。
初等教育課程では、休み時間になると学級ごとにまとまって移動し、教室の外の広いスペースで食べたり飲んだりします。
その際、お菓子の包装紙やペットボトルのごみは必ず出ますが、ごみ箱がすぐ近くにあればポイ捨てをしなくなるのではないかと、一部の担任が考えました。
そして一部の学級では、教室に置いてあるごみ箱を、おやつを食べる場所へ持っていくようになりました。
それは今も継続的に行われています。
(5) 環境に関する教育内容の充実
理科や芸術の授業で、ごみのポイ捨てや環境の大切さを主題にした制作(ポスターや動画の作成、工作 等)がよく行われるようになりました。
配属先の児童・生徒は制作活動が好きで、得意な人が多いです。
その制作を通して、環境への思いを巡らせる機会が増えれば良いなと思います。
行動変容と言いましても、まだまだ小さなことばかりですが、ごみのポイ捨てが少しずつ減っていけば良いなと思います。
環境教育に関しては、年齢が低いうちからやっていくことが大切だと、1年目を通してよく思いました。
次回は、配属先での活動時間外における、任地の人々との交流についてご紹介しようと思います。
過去の記事
環境教育/コロンビア日記1(任地紹介)
SHARE





