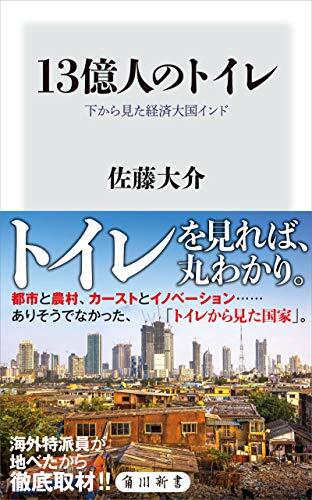2025/02/15 Sat
社会
「13億人のトイレ」を読む 1
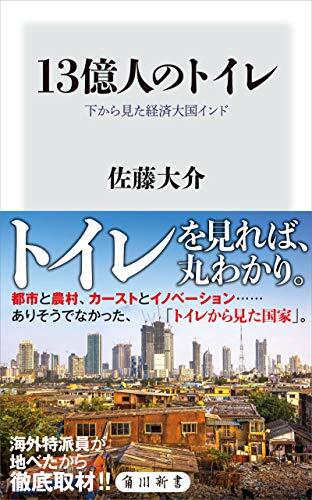
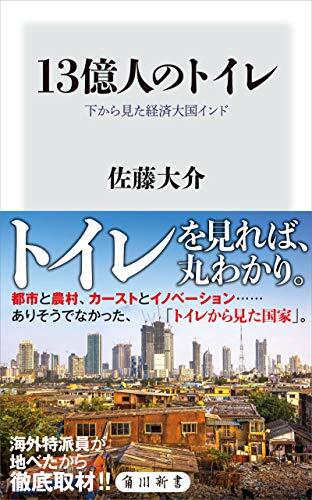
日本は、コンビニやスーパー、お店などにきれいなトイレがたくさんあり、どこに行っても快適にトイレが使える、言わばトイレ天国です。インドは真逆で、日本感覚で使えるトイレはデリーの街にもほとんどありません。海外協力隊員の中には、外出する際、トイレットペーパーはもちろん、下痢止めを持って行く人もいるくらいです。
さて、この本「13億人のトイレ」はJICA事務所で借りて読んだのですが、とても面白い本でした。モディ首相がインド中にトイレを作ったことは知っていましたが、「それはいいことだ」くらいにしか思っていませんでした。実情がどういうものか全然分かっていなかったのです。以下、本の内容をまとめてみました。
そもそも、インドのトイレ事情がどうなっていたのか見てみると、2011年のインドの国勢調査によれば、トイレを持たない家庭の割合は53%もありました。信じがたいことですが、なんとインドの半数以上の家庭がトイレのない暮らしをしていたのです。下の図を見ると、世界の野外排泄人口の半分以上がインドになっています。
その一方で、インドの携帯電話の契約件数は2018年には11億件を超えています。つまり「家にトイレはないけど、携帯電話ならある」という、日本人から見ると非常にいびつな状況があったのです。
モディ首相は2014年に「スワッチ・バーラト」(クリーン・インディア)を掲げて、5年以内に「約1億2000万基のトイレを新設する」「野外排泄を0にする」という政策を行いました。1世帯当たり1万2000ルピー(約2万円)の補助金を出し、5年間でなんと3兆円以上の予算を使うまさに史上最大のトイレ作戦でした。
そして、モディ首相は、2019年10月2日、ガンジーの誕生日に、2万人の観衆の前で「5年間で6億人にトイレがもたらされ、1億2000万基以上のトイレが新設された。女性たちは野外排泄のため暗くなるまで待つ必要がなくなった。不衛生による病気で何十万の命が奪われていたが、今は助かっている。」とスワッチ・バーラトの成功をアピールしました。
実情はどうだったのでしょうか。
飲料水衛生省のまとめによると、これまでに9200万のトイレが設置され、36の州・連邦直轄地のうち、27が「屋外排せつゼロ」の宣言をしました。インド全体で98.9%の世帯がトイレにアクセスできるようになり、特に農村部では昨年の77%から93.1%へ飛躍的に伸び、政策の効果が表れていることを強調しています。

では、なぜ、せっかく作ったトイレを使わないのでしょうか?
単に面倒と言うだけでなく、ここにはヒンドゥー教の浄・不浄の考え方が入り込んでいるから深刻な問題です。
ちなみに、野外排泄についてはいろいろな問題があります。健康面のリスクとしては、野外排泄により地面や川に浸透した病原菌が人々の健康を害します。5歳未満の子ども達が命を失う原因としては、けがやはしかなどより下痢の方が多いのだそうです。
安全面のリスクとしては、蚊にさされたり、時には毒蛇や毒虫にさされる場合もあります。また、女性の性的被害も深刻です。女性は安全のため、一日一回早朝か深夜に用を足しに行くのだそうですが、それを狙って女性をレイプする犯罪者が多いといいます。もし家にトイレがあれば、レイプ犯罪は半減すると警察幹部が話しているのだそうです。
実際、国際機関の調査では、最も貧しい州のひとつビハール州で主婦の85%がトイレにアクセスできておらず、調査したトイレのない家庭のうち、「健康のためにトイレが欲しい」と答えたのはわずか1%で、49%が「安全のため」と答えたのだそうです。
インドは2022年のレイプ犯罪数が3万1000件もあり、レイプ犯罪の多い国です。昨年8月、コルカタの大学病院で働いていた女性研修医が病院内でレイプされて殺害されるという事件が起き、研修医連盟は、犠牲者に対する正義と公立病院の治安改善を求めるストライキを行いました。

SHARE