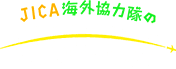2019/06/07 Fri
人 活動
JOCV&NPO法人あおぞらコラボ新生児蘇生講習会inLAOS
6月3日に配属先のパークグム郡病院でNPOあおぞらとラオス医療系JOCVのコラボで郡病院とヘルスセンターの医師・助産師・看護師を対象に新生児蘇生の講習会を行いました。
私とNPO法人あおぞらとの出会いは、2019年3月(赴任して1年9か月目)。配属先の病院へ知り合いのラオス人の医師が日本人3名を連れてやってきました。その日本人こそがNPOあおぞら。なぜここへ?今思うと、これが私にとって衝撃の出会いとなったのです。そこから3人に色々とお話を伺い、ラオスに来た経緯(いろいろと皆さん経験が濃い…)や、当NPOが現在行っているカンボジアの保健センターの設立後のスタッフへの新生児蘇生の普及活動などについて知りました。そして、偶然やパッションが重なり、このラオスの地で私たちとNPOあおぞらとの協働で、新生児蘇生の講習会を実施する経緯に至ったのです。
そこで今回は、その講習会についてと、なぜそもそも私がラオスで新生児蘇生をやりたいと思ったかのきっかけをお話したいと思います。
今回は過去最長の文になりそうなのでご注意ください…
まずそのきっかけですが、JICA海外協力隊として、ラオスのパークグム郡病院に赴任後4ヶ月ほどたった時、新生児仮死の赤ちゃんの症例に出会ったことが始まりです。
当日は、ラオスの国立記念日で病院はお休み。夜自宅にいると、夜勤だったカウンターパートから「赤ちゃんの具合が悪いから病院に来てほしい。」との連絡が入りました。私が到着した時には、赤ちゃんは真っ白な状態で、すでに呼吸がなく、心拍がわずかにある状態。スタッフは緊急処置の棚から人工呼吸のためのバッグやマスク、聴診器などを持ってきていましたが、上手く蘇生ができず、生まれてから約20分程度が経過しているということでした。
これまで私は、心肺蘇生が実施されないまま20分ほども経過した赤ちゃんに遭遇したことはなく、このような状況でどのように対応すべきか悩みました。しかし、今目の前にいる心拍がわずかでも動いて生きようとしている小さな命に対して何もしないという選択肢は私にはありませんでした。私は用意されていた蘇生の物品を使って自分の今までやってきた経験を思い起こしながら病院スタッフと共に必死に蘇生にあたりました。
その結果、心拍は上昇し、呼吸は弱いながら戻って来たのです。私にとってもこのような経験は初めてで、本当に命の逞しさというものを強く実感しました。スタッフも、半ば諦めていたようだったので、人工呼吸で患児の状態が良くなることに少しびっくりしているようでした。その後、心拍や呼吸が戻りましたが、この病院では、呼吸も安定せず、仮死状態の時間が長かった赤ちゃんの経過を見ることが難しい状態でした。その病院には、小児の集中治療室などがないためで、首都の専門病院へ搬送することしか方法はないと思われました。このような経過や状況について、私のカウンターパートである助産師が家族へ説明をしました。ここで大きな問題が起こりました。家族は搬送を拒否したのです。
理由はお金がないからということでした。
最終的には、病院長と私のカウンターパートが家族を説得し、住んでいる村の支援制度などを活用して中央病院で治療できることになり、大きな病院へ搬送されることになりました。でも、これでハッピーエンドでは決してありません。
この時私は思いました。赤ちゃんの治療にかかる費用は今後どうやって捻出するのだろう。もし、赤ちゃんに障害が残った場合、赤ちゃんの人生や、家族の人生はどうなるのだろう。今のラオスで十分福祉がうけられない状況が現実であり、その中で人生を歩み始めた命は果たして幸せなのだろうか?
自分が関わった行為が『目の前の命を救いたい』というただの思い上がりで、ひょっとすると何もラオスのことも知らない自分のエゴだったのかもしれないと、自分自身が行ったことが正しかったのか悩みました。自分の『当たり前』と思っていたことが、ラオスでは決してそうではない現状で、自分の無知によってひとつの命の人生を変えてしまうようで怖くなりました。
それと同時に、ラオス人にとっての「命」ってなんなんだろう、とも考えるようになりました。
しかし、ラオスに住み、生活して思うのは、やはり命の尊さは同じであるということ。命を失った悲しみはラオス人も日本人も他の国も同じということ。医療の現場にいて、未受診妊婦さんや、望まない妊娠をし、安易に中絶を希望する女性などを見て、「命が粗末に扱われている、命を大事にしないラオス人。」などとこの時までは思うことが多々ありました。しかし、大切な人を失って悲しんでいる姿や、子供を大変に心配する心、自分の苦労も厭わず相手に尽くす姿も同時に目にしてきて、これは決して命を粗末にしているのではなく、経済的なことや環境などが大きな原因であり、彼らは自分たちではどうしようもなく選択肢が極めて少ない状況で生きているのかも…感じるようになりました。
一定水準の教育を受けられ、皆保険制度で病院受診のハードルがそれほど高くない日本とは異なるのです。しかし、命を救いたい気持ちは同じです。だからこそ、わたしが蘇生現場に行ったとき、どうにかしなきゃ、とスタッフが処置道具を用意していたのです。しかし、やり方が分からない、手が出せない、彼らは自信がなかったのです。
赤ちゃんの中には、悲しいですが、先天的な理由やお産の時の状況で、救えない命ももちろんあります。でも、救える命ももちろんある。途上国での新生児死亡の原因の24%は分娩時の合併症または、新生児仮死が原因と言われています。新生児仮死であっても、適切なタイミングで適切な処置を行えれば、90%は救うことができると言われています。蘇生技術や一連の流れをスタッフが習得すれば、もっとラオスの赤ちゃんの命は救える。
これまでも私はスタッフが手技を獲得できることを目標に掲げて活動を実施してきました。今までにも病院内での勉強会を計画し、資料を準備してきました。しかし日程がなかなか決まらない、せっかく決まった日も当日になって突然のキャンセル…、勉強会よりも妊婦健診やお産のほうを見てくれていたほうが助かる!とまで言われ、私のやる気もどんどんなくなっていったのです。
でも、協力隊としてのメリットは、現地の人と毎日一緒に働くことです。妊婦健診の空き時間に、興味のあるスタッフと人形を使って人工呼吸の練習、心臓マッサージの方法などを実施しました。そして、お産の時にはできるだけ現場に立ち会うようにしました。
ある時、朝の申し送り時に、夜勤で新生児蘇生が必要な場面があったけれど、マスクのサイズが合わずうまく換気ができずに蘇生がうまくいかなかった事例があったとの問題が挙がりました。と思ったら、急に、「エミ、いまから30分後に勉強会をやって。」と言われることもありました。「えぇっと…。今からですか。。?」ラオスあるある話で急に決まる。という話は何度か耳にしていましたが、「あぁ、このことだ…」と瞬時に理解できました。日本とは違う文化の中で葛藤しているそんな時、ついにこれまでずっと日の出を見ることのなかった資料やアンケートがついに出番を迎えたのです。
その勉強会の開催は、赴任して1年2ヵ月目のことでした。
しかし、その頃は、母子手帳や妊婦さんへの保健指導の活動に集中的に取り組んでいた時期でもありました。この新生児蘇生の勉強会は、何とか1回開催できたことでで、私の中ではをやりきった感があり、その後そのモチベーションを持つこともなく、その後は実施には至っていませんでした。


それからしばらくして、赴任1年9か月目の2019年3月、冒頭で述べたNPOあおぞらとの出会いがあったのです。新生児蘇生のことをなんとなく、やりっぱなしにしていた自分に気が付いたと同時に、自分が本当にやりたかったことはスタッフが今後自分たちで処置できるようになることで、「私が活動(勉強会)をやった!」という達成感ではないことに改めて気づいたのです。そして私自身のラオスでの任期が終わるまでそのNPOと一緒に活動をやっていきたいと感じるようになりました
講師を担ってくれた嶋岡先生は、日本だけではなく、ブータンやカンボジアでも新生児蘇生の講習会を行っており、途上国での新生児蘇生法の普及に力を入れている小児科医でした。私は日本のガイドラインに基づくNCPR法で指導していました。一方でラオスのスタッフはWHOの推奨するEENC(Early Newborn Essential Care)という方法で学習をしていました。EENCがあることもスタッフがそのWHOの方法で習っていることも知っていましたが、そもそも私は日本のやり方を持ち込み教えていたんだということに今回の勉強会を機に初めて気が付きました。また、講習前の打合せではNPOとJOCVで、受講者に理解してほしい考え方や、取得してほしい技術、デモンストレーションの時に注意すべき点を講師の嶋岡先生から伺いました。さらに「それをどうしてやるのか、ラオ人に聞いてみたことはある?」と嶋岡先生に問われたのですが、実はその問いにドキッとしました。今まで、ラオス人のやり方に対して、いつも、なぜ言ったとおりに実施しないのだろうと思っても、どうしてそうするのか?…一つ一つ私が確認していなかったことに気が付いたのです。医療者に取って傾聴が大切であるということに頭では理解しているつもりでも、実際は実施できていなかった。こんなにもラオス人と時間を共に過ごしてきたのに、あまり彼らのの考えに耳を傾けていなかったことを反省しました。日本とラオスは環境が違い、また価値観や考え方も違う。ここで学んだことは、現地の人がなぜそうするのか、理由を聞いてみることや、複数のパターンを取り入れるシナリオ学習の時は、参加者がどういった環境で働いているのか、働いている病院にはマスクや酸素はあるのか、その人のいる環境に合わせてデモンストレーションを行うことで重要であり、参加者が研修会の後もその方法で病院でも実際に実施できる学習になるようにすることです。医療技術だけでなく、教え方そのものについても大切であることを改めて知りました。
シナリオ学習の進め方については、ヘルスセンターのスタッフからは、蘇生のバッグやマスクは揃っているが、マスクが赤ちゃんのサイズに合っていいないため、有効に人工呼吸ができなくて困ることがあるや、実際に一人で対応せざるをえない時があるなどという意見が出ました。そのため、マスクの物品確保の方法をスタッフと相談したり、一人で行う時の方法などを練習するなど、現場レベルに沿った学習をすることで、ラオス人が主体になり、問題を明確化し、解決策を導き、実践に繋げられることを学びました。
新生児蘇生法については、赴任当初に、蘇生が必要なケースで、スタッフが躊躇してしまった場面を見たことから必要性を感じ、取り組みたいと考え活動してきました。しかし、「何か正しいことを教えないと!」と思ってしまい、数値や技術などにこだわってしまっていることが多かったです。しかし、今回の講習会のコースの組み立てを通して、スタッフ自身が「私ならできるかも!やれるかも」と思える成功体験を持ってもらうことで、これまで現場で躊躇して対応できなかったスタッフから、講習会実施後には「自信がついた」という感想を聞くことができ、これこそ、「技術移転」なのだなと感じました。技術移転とは、正しいことを教えることではなく、一緒に対話をし、現場レベルで考え、今までの互いの価値観や心を変えることであると教えてもらいました。
最後に。協力隊としてラオスに来て、蘇生の概念の違いや、経済的な負担から蘇生を望まない場合のケースなども目にして自分の無力さや心苦しさを感じることもありました。しかし、そのような思いは、ラオス人はあまりなく、平気な顔をしたり、シリアスな状況でも冗談などを言い仕事をしている姿を見ると「命への感覚」というものが違うのだろうか?と感じることもありました。一方で、命を救えなかったことに落ち込んでるスタッフの姿を見たこともありました。様々なケースの中にいる医療者としてラオスの人の思いもそれぞれで、「本当は救いたい」と願っていても、結局、それができない環境であったり、国の制度であったり、文化であったり、どうしようもない理由が隠れていることも、この協力隊生活を通じて見えてきたように思います。
新生児蘇生においては、正しい技術を提供して命を救うことも重要ですが、そのような現実と向き合っているラオス人医療者の心の支援をすること、また辛い体験や思いにも寄り添い支援していくことも技術以上に大切であることを今回の講習会では考えさせられました。
なお、今回の講習会は私一人で行ったのではなく、他の医療系JOCVとも協働して実施したものです。あるJOCVは自分が所属する病院で使われていなかったシミュレーション用の新生児人形を発見、あるJOCVはスタッフへ蘇生の経験などを調査して今後の指導の必要性を検討すると言っています。異国の地で活動をするということは大変なことも多いですが、私たちはそれぞれの思いを胸にそれぞれの任地で頑張っていこうと励ましあっています。自分たち、そしてラオスのこれからの将来にも希望が見えた気がしています。
SHARE